
「花の梅園」
大分県日田市大山町おおくぼ台で、梅栽培を始めて60年余り。
2月中旬〜3月中旬は、「日田おおやま梅まつり」が開催され、多くの人が訪れます。梅の花の美しさ、樹の勇ましい存在に魅了されます。 |

「老木の梅」
この梅の樹は、樹齢59年です。まだまだ元気です。
旧大山町の、梅栗運動の歴史とともに、活躍してきました。 |
「我が家で栽培している、主な梅の品種とその特徴」
|
●南高梅
果実は大粒でうっすらとした皮の内側には、とろけるほどのやわらかい果肉がつまった、梅干しの原料となる代表的な品種。我が家の梅干しでも代表的な品種。6月中旬〜下旬にかけて収穫します。
●鴬宿梅
果実は深い緑色で、果肉が固く、芳香とコクのある梅酒の原料として最適な品種。大山町が昭和36年に梅栽培を始めたときからのルーツともいえる品種。5月下旬〜6月上旬にかけて収穫。
●七折小梅
小梅種の中でも、比較的大粒の一口サイズの梅。果肉がやわらかく、肉厚の品種。6月上旬頃に収穫。
●光陽小梅
小梅種。小粒であり、梅干し加工の食品やお菓子などによく利用される。5月中旬に収穫する品種。
|
|
 「収穫間近 「収穫間近
の南高梅」
たわわに実った梅の実。
太陽の光を浴びて、赤く色づきます。
しかし、まだまだ完熟を迎えるまで待ちます。 |

「いよいよ収穫」
黄色味を増し完熟したら、ひと粒一粒、丁寧に収穫します。 |
|
「原料はきれいに洗浄」 |
|
「我が家仕込みの最高の塩梅」で漬け込み |
|
梅干し造りに欠かせない、
「三日三晩の天日干し」
|
| |
 |
|
 |
|

三日三晩の天日干しは、太陽の光を梅の両面にまんべんなくあたるようにします。 |
|
収穫した梅を、きれいに水洗いします。 |
|
水洗いした梅を、海水から製塩したミネラル豊富な、高級塩で塩漬けします。 |
|
樽上げされて、再び、真夏の太陽の光をさんさんと浴びて、太陽の香りを包み込んだ梅干しになります。 |
|
 |
| 蔵の中でさらに自家製の紫蘇とともに漬け合わせて本格派の梅干しに仕上がって行きます |
|
樽の中で、静かに時を刻みます。 (熟成されます) |
 |
|
 |
| 自家製しそで本漬 |
|
新しい年が来るまで、およそ4ヶ月間樽の中に漬け込まれます |
|
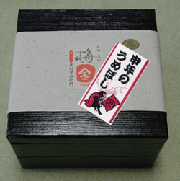 「申年の梅干しの云われ」 「申年の梅干しの云われ」
古来より、梅の実を食に取り入れていた地域は、日本に限らず中国やお隣韓国など、梅の実にまつわるお話は様々あるようです。平安時代の申年に疫病が流行した時、時の村上天皇が梅の実で人々の命を救い、自らの病気も梅の実を食べて直したと云われています。徳川家康が江戸入城の時、病気で瀕死のウマをサルに近づけたところ、たちまち元気になったとも伝えられています。それ以来、申年の梅は薬になると重宝されたそうです。実際にサル年には梅の収穫量が少なかったようです。
サル年の梅でウマ年の病気を治すといった事が今に伝えられているのでしょう。
|
|
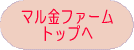 |